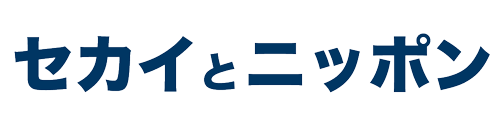日米中ではどれくらいの資産があれば「富裕層」と呼ばれるの?
「富裕層」という言葉には複数の定義がありますが、日本では「野村総合研究所」による「純金融資産保有額が1億円以上5億円未満」を富裕層とする定義が一般化しています。
野村総合研究所によれば、日本には2021年時点で139.5万世帯の富裕層が存在しており、この数は「安倍政権の経済政策(アベノミクス)が始まった2013年以降、一貫して増加を続けている」そうです。
また、富裕層の数だけでなく、金融資産総額も13年以降は年々増加しています。2024年9月時点の日経平均株価は2021年を大きく上回っていることから、日本では富裕層の資産総額は21年時点よりさらに増えていることが予想されます。
世界的な株高により、富裕層が増えているのは世界的な流れとも想定できますが、世界一の経済大国である米国と世界2位の中国では富裕層はどのように定義され、どれくらいの数が存在するのでしょうか。
米国でも富裕層の定義は1つではありませんが、金融資産の分野では「全体の上位1%」に含まれる人びとを富裕層とする定義がよく見られます。米国の不動産会社ナイト・フランクがまとめた2024年の「ウェルス・リポート」では、米国で「全体の上位1%」に入って富裕層と見なされるためには、最低でも「580万ドル(約8億2940万円)」の純資産が必要だと指摘しています。
また、100万ドル(約1億4000万ドル)を超える流動資産を持つ家庭を富裕層とする見方もあり、この定義の場合は米国には富裕層が550万世帯も存在するそうです。なお米国も日本同様、富裕層の数と資産は増加傾向にあると言われています。
次に、国内総生産で世界第2位の中国の場合を見てみます。社会主義国の中国にも富裕層に関する公式の定義はありませんが、民間シンクタンク「胡潤研究院」は資産額が600万元(約1億2000万円)を超える世帯を富裕層と定義しています。
中国国家統計局によると、中国の2023年の1人当たり可処分所得は3万9218元(約80万円)だったことから、中国で富裕層になるのは日本や米国以上に難しいと言えそうです。一方で、中国では富裕層の数が減少しているということは注目すべき点でしょう。
2023年時点の中国では富裕層に該当する世帯が514万世帯も存在しましたが、その数は22年に比べて0.8%減少したほか、1億元(約20億円)を超える資産を持つ超富裕層は3.8%も減少しました。こうした富裕層の数の減少は中国経済の減速を示していると言えるのかもしれません。