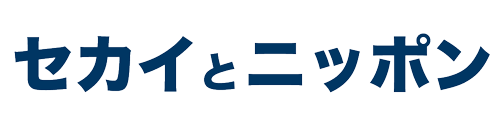控除額「103万円」で固定されてきた日本、世界では控除額が調整されるのが一般的?
「103万円」という数字が大きな注目を集めています。現在の日本では年収が103万円を超えると、超過した金額に対して所得税がかかることになります。また、学生などの被扶養者の場合、年収が103万円を超えると、親など扶養者の税負担が増えることになり、こうした控除の上限額が「103万円の壁」と呼ばれています。
日本は長らく控除額が103万円に固定されてきた国ですが、日本以外の国は所得税に対する控除額は一般的に固定されているのでしょうか。それとも自動的に調整されるのが一般的なのでしょうか。
世界には所得税に対する控除額が物価上昇率に応じて毎年調整される国があり、その代表的な国としては米国とカナダが挙げられます。
米国の場合は「連邦所得税」と「州所得税」があり、そのどちらにも控除額が設定されており、州所得税に対する控除額は州によって大きく異なるものの、連邦所得税に対する控除額は全米で一律となっています。
米国内国歳入庁(IRS)によれば、2023年の世帯主の場合は控除額が20,800ドル(約322万円)、夫婦合算の場合は27,700ドル(約429万円)に設定されており、この控除額は物価上昇などに応じて毎年、自動的に調整されるのが特徴的です。
JETROによると、23年の夫婦合算の「27,700ドル」という控除額は、前年に比べて1,800ドル(約27万9000円)も増加しています。米国の場合はインフレが深刻だったという事情もありますが、たった1年で控除額が約27万9000円も増加するというのは、日本の現状からすれば驚きです。
日本は物価上昇に応じて控除額が自動調整されない国であるものの、長らく物価下落が続いてきた以上は仕方がないことと言えるでしょう。また、日本と同じように控除額が自動調整されない国としては韓国やニュージーランド、イタリアなど多くの国が挙げられ、米国のように控除額が自動的に調整される国はむしろ少数派のようです。
参考文献